小学生でスマホを持つのが当たり前の時代
近年、子どもたちが初めてスマートフォンを持つ年齢は、どんどん低くなっています。 文部科学省の調査によると、令和3年度には、小学生の約半数が、スマートフォンを所有しているというデータもあります。 特に、小学校高学年になると、クラスのほとんどの子が持っている、という状況も珍しくありません。
子どもがスマホを持つことには、メリットもたくさんあります。 緊急時の連絡手段として、GPS機能で子どもの居場所がわかる安心感。 知的好奇心を刺激する様々な情報や、学習アプリの活用。 そして何より、友達とのコミュニケーションツールとして、子どもたちの世界を広げてくれる力があります。
しかし、その一方で、保護者の皆さんは、こんな不安を抱えてはいませんか?
- 「インターネットの世界には、危険がいっぱいなのでは?」
- 「有害な情報に触れてしまったらどうしよう…」
- 「知らない人と繋がって、犯罪に巻き込まれたら…」
これらの不安は、わが子を思う親心として、当然の感情です。 私も、スクールカウンセラーとして、保護者の皆さんのご心配をひしひしと感じています。
親はわが子を守りたい。でも、その思いが家庭を壊すことも?
「安心フィルター」という魔法の言葉
そんな保護者の皆さんの不安を解消してくれるものとして、多くの携帯会社が提供しているのが、**「安心フィルター」**です。
これは、子どもがインターネットを利用する際に、不適切なウェブサイトやアプリへのアクセスを制限したり、利用時間を管理したりする機能のことです。 「これさえつけておけば、うちの子は大丈夫!」 「有害なものから、しっかり守ってくれる!」 そう考えて、スマホを買い与える際に、安心フィルターを搭載する保護者の方は少なくありません。
しかし、私は、スクールカウンセラーとして、あえて警鐘を鳴らしたいのです。 その「安心フィルター」が、実は、家庭を壊す引き金になっているケースが後を絶たないという事実を。
「安心フィルター」が生む新たな問題
なぜ、子どもの安全を守るはずの安心フィルターが、家庭を壊してしまうのでしょうか。 それは、安心フィルターがもたらす、複数の問題が複雑に絡み合っているからです。
1. 厳しい「縛り」が子どもの心を蝕む
安心フィルターを搭載する際、保護者の方々は、様々な制限を設定します。 利用時間の制限、アクセスできるサイトの制限、アプリのダウンロード制限など。
しかし、その制限があまりにもキツすぎると、どうなるでしょうか。
子どもたちは、友達と話題を共有したいのに、YouTubeが見られない。 友達がやっている流行りのゲームを、自分だけダウンロードできない。 宿題で調べたいことがあるのに、特定のサイトがブロックされていて、情報収集ができない。
このような状況が続くと、子どもは「自分だけ仲間外れだ」「自分だけ自由にさせてもらえない」と感じるようになります。 そして、その不満や孤独感は、やがて保護者に対する反発心へと変わっていきます。
- 「どうして僕だけダメなの?」
- 「お母さんは、僕のことを信用してくれないの?」
- 「もう何も話したくない…」
子どもの心を縛り付けるような厳しい制限は、保護者との信頼関係を少しずつ壊していくのです。
2. いじめの原因にもなる「不自由なスマホ」
私は、日頃から学校で、子どもたちのいじめ問題に直面しています。 そして、現役で子どもたちを支えている教育支援員さんたちと話す中で、ある恐ろしい事実を共有しています。 それは、最近のいじめの原因の、実に大半がスマートフォンに関わるものであるということです。
「LINEのグループで仲間外れにされた」 「ゲーム内で課金していないことをからかわれた」 「SNSに悪口を書かれた」
このような、スマホを介した新しい形でのいじめが、日々発生しています。
その一方で、私と教育支援員さんたちは、スマホを持たされていない子よりも、スマホを買い与えられたのに、安心フィルターによって何もできない子の方が、いじめのターゲットになりやすい、という見解で一致しています。
なぜなら、スマホを持っていない子には、「かわいそう」「家が厳しいのかな」といった同情の念が集まることが多いからです。 しかし、スマホを持っているのに、ゲームもできない、SNSもできない、友達とのやり取りもままならない。 そんな子は、周りの子たちから「なんだよ、つまんないやつ」「ダサい」といったレッテルを貼られ、いじめの対象になってしまうリスクが高いのです。
保護者としては、「いじめから守るために」という善意で安心フィルターをつけているのに、それがかえって、いじめの原因になってしまう。 なんとも皮肉な話ですが、これが、現代の学校で起きている現実なのです。
「じゃあ、スマホを買い与えなければいいのでは?」という問いへの答え
ここまで読み進める中で、「じゃあ、そもそも子どもにスマホを持たせなければいいのでは?」と思った方もいるかもしれません。
しかし、私は、その考えにも異を唱えたいのです。 なぜなら、スマホを持たないことは、子どもの成長にとって、大きなマイナスになる可能性があるからです。
子どもは、友達とのコミュニケーションを通して、社会性を身につけていきます。 しかし、周りの子がみんなスマホを持っているのに、自分だけ持っていない。 そうすると、友達との会話についていけなくなり、交友関係が狭まってしまいます。
「昨日、あのゲームでさー」 「え、何それ?僕、持ってないからわからない…」 「LINEのグループ、知ってる?」 「ううん、入れてないんだ…」
このような疎外感は、子どもの心を深く傷つけ、自己肯定感を下げてしまいます。 また、将来、大人になって社会に出たとき、私たちはインターネットの世界を避けて通ることはできません。 仕事でも、プライベートでも、スマートフォンは必要不可欠なツールです。
成人してから初めてネットの世界に触れるのと、子どものうちから少しずつ学んでいくのとでは、大きな差が生まれます。 危険な誘惑を避け、正しい情報を取捨選択する力。 SNSで、誰かを傷つけることなく、円滑にコミュニケーションをとる力。 そうした**「ネット社会を生き抜くためのリテラシー」**は、子どものうちから、実践を通して身につけていくべきなのです。
大切なのは、教えて育てる「ネット教育」
私は、断言します。 子どもたちをネットの危険から守るために最も重要なのは、**安心フィルターを搭載することではなく、ご家庭でしっかりと「ネットの世界について教育すること」**です。
これは、難しいことではありません。 しかし、残念ながら、今の安心フィルターは、この**「ネット教育」を実践する上で、あまりにも機能が不足しています。**
安心フィルターが「ネット教育」を妨げる理由
安心フィルターの多くは、「ブラックリスト方式」と呼ばれる方法で、有害サイトをブロックしています。 つまり、事前に「これは有害だ」と登録されたサイトだけを、アクセスできなくする仕組みです。
しかし、インターネットの世界は、日々、ものすごい速さで変化しています。 新しいサイトやSNSが次々と生まれ、有害な情報も、巧妙に姿を変えて現れます。 安心フィルターのブラックリストは、そのスピードに追いつくことはできません。
その結果、どうなるでしょうか。 子どもたちは、**安心フィルターの「抜け穴」**を簡単に見つけてしまいます。
- 「VPNを使えば、ブロックされたサイトが見られるんだって」
- 「プロキシサーバーを経由すれば、バレないらしいよ」
子どもたちの情報収集能力は、驚くほど高いです。 そして、抜け穴を見つけた子どもは、保護者に対して「どうせ安心フィルターなんて意味ないじゃん」という不信感を抱くようになります。
アプリのレビュー欄を見るだけで、そういった情報は目に入ります。
さらに、安心フィルターは、一般的に必要とされる教育アプリケーションや、辞書サイトまで、有害認定してしまうことが、しばしばあります。 「勉強のために辞書サイトを使いたいのに、ブロックされてしまった」 「プログラミング学習のアプリをダウンロードしたいのに、許可されない」 このような不便さは、子どもの学習意欲を削ぎ、保護者との軋轢を生む原因となります。
安心フィルターは、あくまでも「機械による一方的な制限」に過ぎません。 そこに、「なぜこのサイトはダメなのか」「どうしてこのアプリは危険なのか」という、保護者の声かけや、教育的な視点は、一切存在しません。
だからこそ、私は、安心フィルターに依存するのではなく、ご家庭での「ネット教育」を徹底することを、強くお勧めしたいのです。
ご家庭で始める、ネット教育の第一歩
では、具体的に、ご家庭でどのような「ネット教育」をすれば良いのでしょうか。 それは、決して難しいことではありません。 少しの工夫と、保護者の方の「寄り添う姿勢」があれば、誰もが始められることです。
1. 親子で「ネット利用のルール」を一緒に作る
大切なのは、親が一方的にルールを押し付けるのではなく、子どもと一緒にルールを考えることです。
- 「スマホを使うのは、夜9時までにするのはどうかな?」
- 「SNSに、個人の住所や電話番号を載せるのは危ないから、やめようね」
- 「もし、知らない人からメッセージが来たら、まずはお父さんやお母さんに相談してね」
なぜそのルールが必要なのか、その理由を丁寧に説明し、子どもが納得できる形で、ルールを定めていきましょう。 ルールは、紙に書いて、リビングに貼っておくのも効果的です。 そして、そのルールは、子どもの成長に合わせて、柔軟に見直していくことも大切です。
2. 親自身が「ネットの世界」に興味を持つ
子どもがどんなゲームで遊んでいるのか、どんなSNSを使っているのか。 まずは、親自身が、子どものネットの世界に興味を持ち、一緒に体験してみることが大切です。
- 「そのゲーム、面白そうだね!お母さんにもやり方教えてよ」
- 「そのアプリ、どんな風に使うの?一緒にやってみようか」
そうすることで、子どもは「お父さん、お母さんは、自分のことを理解しようとしてくれている」と感じ、安心して、ネットの世界での出来事を話してくれるようになります。
3. 「オープンなコミュニケーション」を心がける
これが、最も重要なことです。 子どもがスマホでトラブルに巻き込まれたり、何か困ったことがあったりしたとき、「お父さん、お母さんに相談したら怒られるかも…」と不安にさせない環境を作ることが大切です。
- 「何か困ったことがあったら、いつでもお話聞くよ」
- 「もし、ネットで嫌な思いをしたら、一人で抱え込まないでね」
そうした日頃からの声かけが、いざという時の子どものSOSを、キャッチする力になります。 そして、万が一、子どもがトラブルに巻き込まれたとしても、決して頭ごなしに怒ったりせず、まずは「大変だったね、怖かったね」と、子どもの気持ちに寄り添ってあげてください。
まとめ:安心フィルターに頼らない子育てを
子どもたちの未来は、無限の可能性に満ちています。 しかし、その可能性を育むためには、**「ネットの世界を賢く生き抜く力」**が、不可欠な時代になりました。
安心フィルターは、確かに、一時的な安心感を与えてくれるかもしれません。 しかし、その代償として、親子間の信頼関係が崩れ、子どもの成長を阻害し、家庭を壊してしまうリスクがあるのです。
安心フィルターに頼るのではなく、親子のコミュニケーションを大切にしながら、ご家庭で「ネット教育」を実践していくこと。 それが、子どもたちをネットの危険から守り、健やかな成長を促すための、最も確実で、最も温かい方法だと、私は信じています。
このブログが、少しでも多くのご家庭の、ネットとの向き合い方を考えるきっかけとなれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

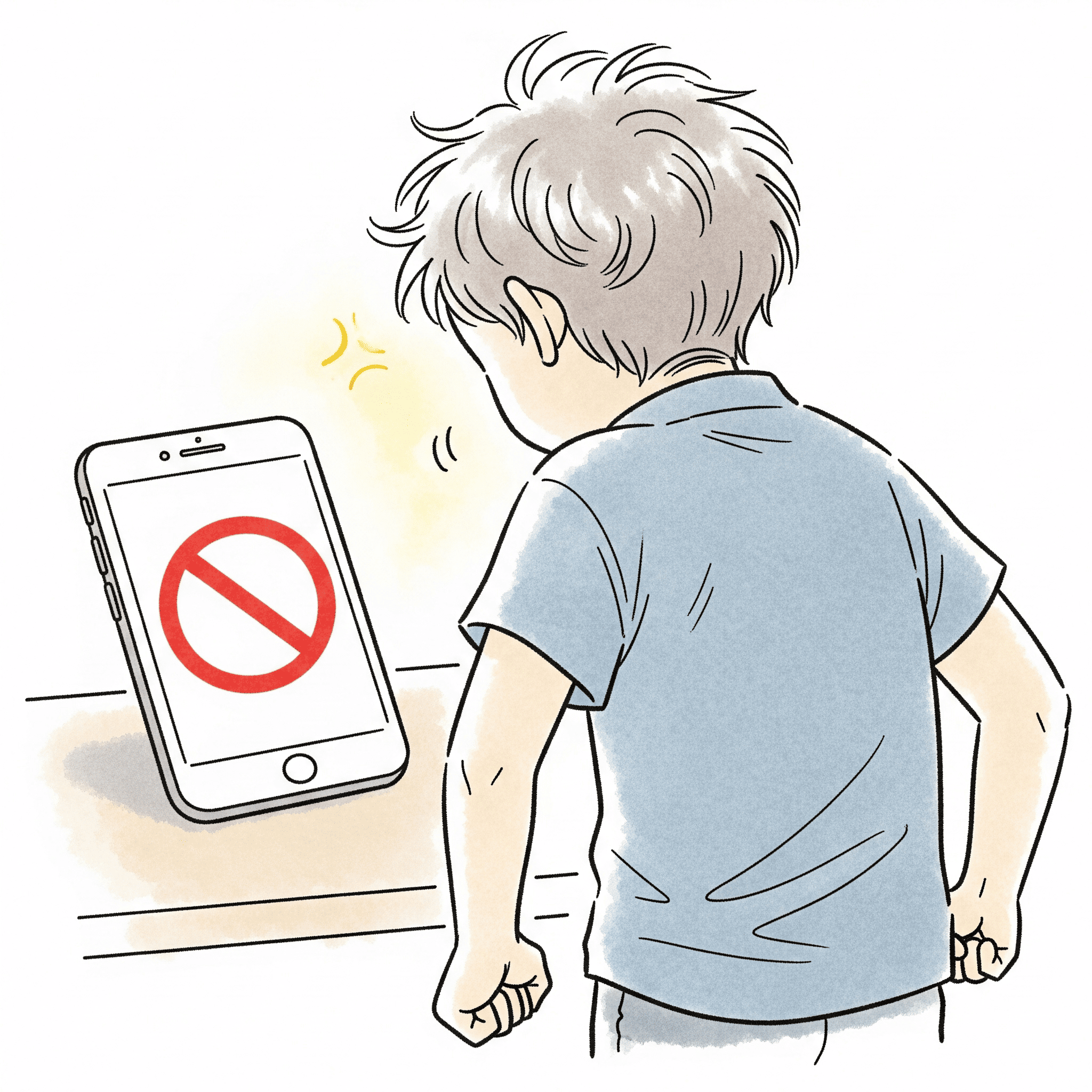
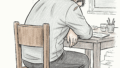
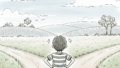
コメント