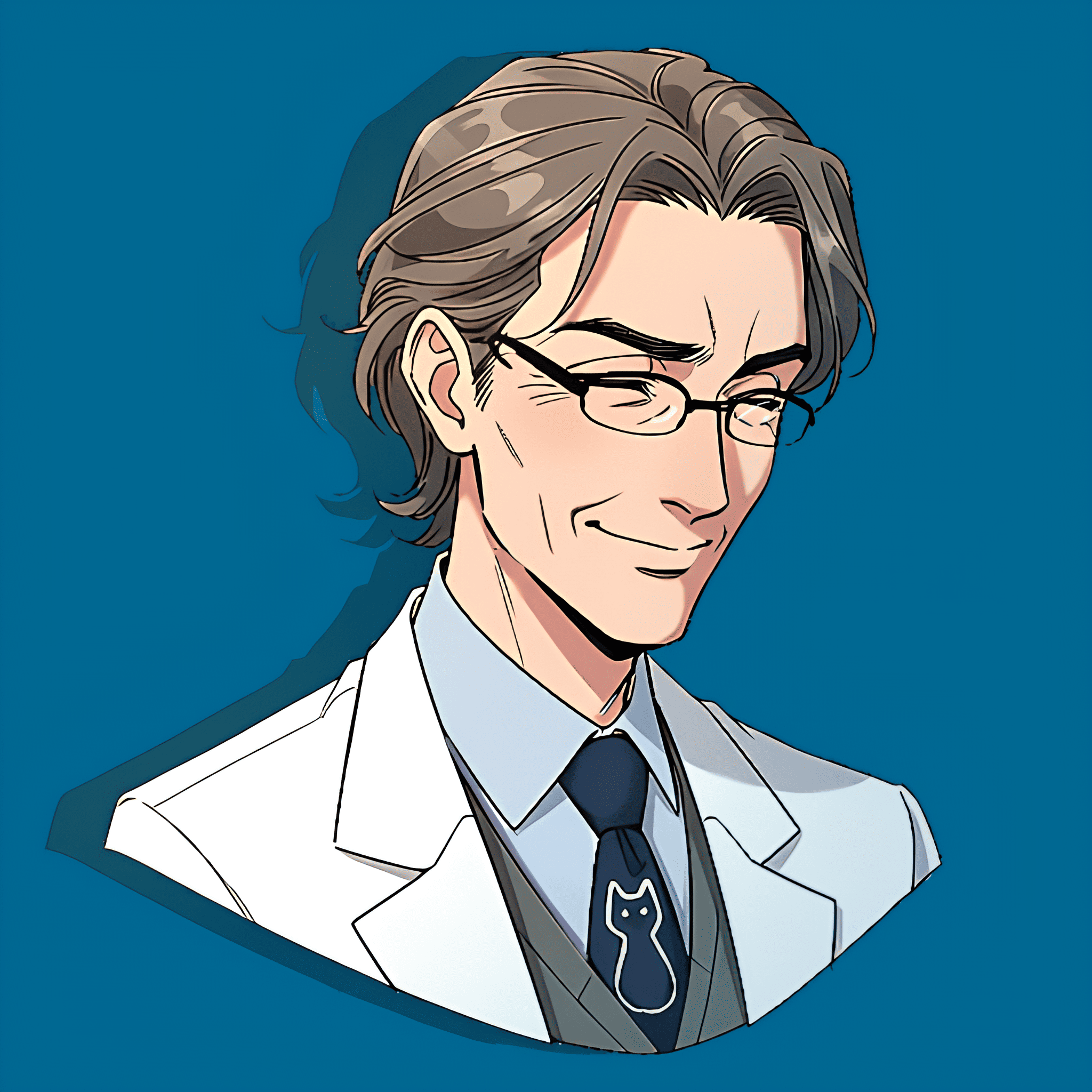
こんにちは!スクールカウンセラーの環(たまき)です。
今日は、少し前に話題になった「キラキラネーム」と、最近よく耳にするようになった「しわしわネーム」について、お話ししようと思います。
変わってきた、名前の悩み
最近、カウンセリングルームに来る子どもたちの相談内容が、少しずつ変わってきているなと感じています。
以前は、自分の名前が読みにくかったり、珍しすぎたりして、からかわれたりすることに悩む子どもたちがたくさんいました。
例えば、「宇宙(コスモ)」くんとか、「心愛(ココア)」ちゃんとか、そんな素敵な響きの名前を持つ子が、からかわれてしまって…という相談がよくありました。
いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる名前を持つ子どもたちです。
でも、最近はそうした相談がめっきり減ってきました。
むしろ、「太郎」くん、「花子」ちゃんといった、昔ながらの名前、いわゆる「しわしわネーム」と呼ばれる名前を持つ子たちの相談が増えているんです。
「なんで私の名前はこんなに古いの?」 「友達はみんな、おしゃれでかわいい名前なのに…」
そんなふうに、自分の名前に自信が持てない、という悩みを抱えている子どもたちが、実はたくさんいます。
キラキラネームとは?
「キラキラネーム」とは、一般的に、当て字や珍しい読み方をする名前のことを指します。
例えば、「愛羅(てぃあら)」さん、「光宙(ぴかちゅう)」くんのように、響きは可愛かったりかっこよかったりするけれど、一見して読めない、少し特殊な名前です。
これらの名前は、親御さんが「誰とも被らない、個性的な名前にしたい」という思いからつけられることが多いようです。
キラキラネームを持つ子どもたちの家庭環境を見てみると、
- 個性を尊重する家庭
- 新しいものや流行に敏感な家庭
- 子どもの可能性を信じ、自由に育てたいと考えている家庭
といった特徴が見られることが多いです。
親御さんの深い愛情が込められている一方で、キラキラネームには、いくつかのデメリットも指摘されてきました。
- 読みにくい・覚えられにくい:初対面の人に名前を呼んでもらうまでに時間がかかったり、何度も読み方を聞かれたりすることがあります。
- からかいの対象になりやすい:特に小学生の頃は、珍しい名前がからかいの対象になることもありました。
- 社会生活での不便さ:就職活動の際に「常識がない」と判断されてしまったり、履歴書の記入欄に名前が書ききれなかったり、といった不便さを感じることがあるようです。
しかし、これらのデメリットを乗り越え、自分らしく生きている子どもたちもたくさんいます。
「名前が珍しいからこそ、覚えてもらいやすい」 「自分の名前は、親が特別に考えてくれた、世界に一つだけの名前なんだ」
現代はそんなふうに、ポジティブに捉えている子も少なくありません。
キラキラネームの子が語る「キラキラでよかった」という話
最近、キラキラネームの子たちと話していると、「キラキラネームでよかった」という声を聞くことがあります。
「え、でも、からかわれたりするんじゃないの?」と尋ねると、意外な答えが返ってきました。
「キラキラでも、しわしわじゃないだけマシだよ」
この言葉には、深い意味が隠されていました。
「しわしわネームは、いざとなっても変えられないけど、キラキラネームは、改名できるから」
この言葉は、私に大きな衝撃を与えました。
しわしわネームとは?
「しわしわネーム」とは、昔からある、古風な名前のことを指します。
「一郎」「太郎」「花子」「幸子」といった、誰もが知っている、伝統的な名前です。
これらの名前は、「誰からも愛される、穏やかな人生を送ってほしい」という、親御さんの願いが込められていることが多いです。
しわしわネームのメリットは、
- 読みやすい・覚えやすい:初対面の人にもすぐに名前を覚えてもらえ、社会生活での不便さはほとんどありません。
- 安心感がある:伝統的な名前は、周りの人に安心感を与え、信頼されやすいというメリットがあります。
しかし、最近は、しわしわネームに悩む子どもたちが増えています。
「友達はみんな、可愛い名前なのに、なんで私だけ…」
そんなふうに、自分の名前を「古い」「ダサい」と感じてしまうようです。
しわしわネームに悩む子どもたちの声
私がカウンセリングで話を聞いていると、しわしわネームの子どもたちが、特に嫌がっている漢字があります。
それが、「子」と「美」という漢字です。
「子」という漢字
「花子」「幸子」「由紀子」など、一昔前には当たり前だった「子」という漢字。
しかし、今の若い世代の子どもたちにとっては、少し抵抗があるようです。
- 「なんか、おばあちゃんみたいで嫌だ」
- 「古臭いって言われるのが嫌だ」
そんな声を聞くことが多いです。
「美」という漢字
「美香」「由美」「美咲」など、「美」の漢字も、昔からよく使われてきました。
でも、この漢字に悩んでいる子どもも少なくありません。
「美しく育ってほしい」
親御さんの願いが込められたこの言葉は、子どもたちにとって、時にプレッシャーになることがあるようです。
「親は私に、美しくなってほしいって思ってるのかな…」 「でも、私はそんなに可愛くないし…」
親の願いが、いつしか自分を縛りつける「呪い」になってしまう…。
そんなふうに、一人で悩みを抱え込んでいる子どもたちもたくさんいます。
しわしわネームの悩みと改名の難しさ
ここ数年で、子どもたちの間には「改名」についての知識が広まっています。特にキラキラネームを持つ子どもたちは、「名前が読めない」「人名としてふさわしくない」といった理由が「正当な事由」として認められやすいことを、ネットや口コミを通じて知っています。
その一方で、しわしわネームに悩む子どもたちは、自分たちの改名が難しいと感じています。
「太郎」や「花子」という名前は、決して奇抜でも難読でもありません。社会生活で不利益を被ることはほとんどなく、むしろ「常識的で良い名前だ」と評価されることも多いです。
しかし、子どもたちが抱える「名前が古臭い」「ダサい」「友達と比べて恥ずかしい」という悩みは、裁判所が認める「正当な事由」にはなりにくいのが現状です。
「正当な事由」がないため、彼らは改名という選択肢を最初から諦めてしまう傾向にあります。
これは、キラキラネームを持つ子どもが「いざとなれば改名できる」と希望を持てるのに対し、しわしわネームを持つ子どもは「この名前で生きていくしかない」という絶望感を感じてしまう要因の一つです。
具体的な改名手続き
名前は家庭裁判所に認められることで改名をすることが可能です。
「名前が珍しすぎて、社会生活に支障がある」
こういった理由で、改名が認められるケースは増えています。
改名手続きは、少し複雑ですが、決して不可能ではありません。
改名については相談が多くあり、ここでは改名手続きについて、詳しくご説明します。
名前を改名する手続き
名前を改名するには、家庭裁判所に「名の変更許可の申立て」を行う必要があります。
- 必要書類の準備
- 申立書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 変更の理由を証明する資料(診断書、いじめの記録など)
未成年者が改名する場合、原則として親権者である親の同意が必要です。しかし、状況によっては親権者でなくても改名手続きを進められるケースがあります。
未成年者の改名と親権者の同意
未成年者(15歳未満)が改名する場合、本人に代わって法定代理人が申立てを行う必要があります。この法定代理人は、通常は親権者である父または母です。
15歳以上であれば、未成年者本人が単独で申立てを行えます。しかし、その場合でも親権者の同意書を添付するのが一般的です。家庭裁判所は、未成年者の意思だけでなく、親権者が子の改名に同意しているかを確認します。
これは、親権者には子の氏名を決定する権利(命名権)があり、改名が親権者の意思に反していないかを確かめるためです。
親権者の同意書がない場合、家庭裁判所は「親権者の意向」を重視します。親権者が改名に反対している場合、改名が許可される可能性は著しく低くなります。たとえ「正当な事由」があったとしても、親権者の反対を乗り越えるのは非常に困難です。
親権者以外の同意で改名できるケース
原則として親権者の同意が必要ですが、以下のような状況では、親権者でなくても改名手続きを進められる場合があります。
1. 親権者がいない場合
- 親が亡くなっている:両親が他界している場合、改名申立ては、未成年後見人など他の法定代理人が行います。
- 親権停止・喪失:親が虐待などで親権を停止・喪失している場合、親権者ではない別の人物が法定代理人として申立てを行います。
2. 親権者が同意してくれない場合
**「親権者が正当な理由なく改名に同意してくれない」**という状況では、家庭裁判所は慎重に判断します。
たとえば、性同一性障害(GID)で名前の変更を強く希望しているにもかかわらず、親が頑なに反対しているようなケースです。この場合、裁判所は子の意思を尊重し、親権者の同意がなくても改名を許可することがあります。ただし、この判断は非常に稀で、医師の診断書や専門家の意見など、客観的な証拠が不可欠となります。
この判断は、子の利益が最優先されるという考えに基づいています。改名しないことによって子が深刻な精神的苦痛を負うと判断された場合、親権者の意向よりも子の意思が重視されることがあるのです。
しかし、あくまでこれは特別なケースです。一般的な名前の不便さなどを理由とする改名では、親権者の同意はほぼ必須と言えます。
- 家庭裁判所への申立て
- 申立書と必要書類を、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
- 審判
- 家庭裁判所が、申立て内容を審査し、改名が妥当かどうかを判断します。
- 裁判官から質問を受けることもあります。
- 許可
- 裁判所が許可すれば、改名が認められます。
- 許可後、市区町村役場に届け出を行うことで、戸籍上の名前が変更されます。
改名が認められるには、「正当な事由」が必要です。
- 珍奇な名前で社会生活に支障がある場合
- 同姓同名が多く、区別がつかない場合
- 読み方が難しく、誤解を招く場合
- 精神的苦痛を伴う場合(虐待をした親と同じ名前で、その名前を呼ばれるたびに精神的な苦痛を感じる)(配偶者の不倫相手の名前を付けられていた)
- 性同一性障害(GID)を理由に、性別と合わない名前から変更したい
など、具体的な理由が求められます。
役所が認めてくれない名前もある?
キラキラネームの話題になると、「どんな名前でもつけられるの?」という疑問が浮かぶかもしれません。実は、戸籍法や戸籍法施行規則によって、名前に使用できる文字や、名前として認められないルールが定められています。
役所(市区町村役場)で出生届を提出した際、もし名前がこれらのルールに反していると判断されると、受理されず、名前の変更を求められることがあります。
これは、親が子どもの名前を自由に決める権利(命名権)と、社会生活における名前の役割(個人を特定し、混乱を招かないようにする)とのバランスを考慮したものです。
ここでは、具体的にどのような名前が認められないのか、いくつか例を挙げて解説します。
1. 人名用漢字・ひらがな・カタカナ以外の文字
戸籍法では、名前に使える文字は以下の通りと定められています。
- 常用漢字
- 人名用漢字
- ひらがな
- カタカナ
これ以外の文字、例えば以下のものは名前に使うことができません。
- アルファベット:例えば、「ジョン」のようにカタカナで表記することは可能ですが、”John”とアルファベットで書くことはできません。
- 記号:星(☆)、ハート(♡)、波線(〜)など。
- 絵文字:これも当然ですが、使用できません。
- アラビア数字:例えば、「二郎」は漢字で書けますが、”2″と数字で書くことはできません。
過去には、漢字の「𠮷(つちよし)」や「﨑(たつさき)」など、常用漢字ではないものの旧字体として人名に認められている文字もありましたが、基本的には人名用漢字表に掲載されている文字のみが使用可能です。
2. 読みが常識からかけ離れている、人名として不適切と判断される名前
これが、いわゆる「キラキラネーム」の議論の中心にもなる部分です。戸籍法には、「人名としてふさわしくない名前」は認められないという規定があります。
具体的には、以下のような名前が該当する可能性があります。
- あまりにも奇抜な読み方:
- 漢字の持つ意味や一般的な読み方から大きくかけ離れている場合です。例えば、「太郎」を「けん」と読ませるなど、読みと漢字の間に合理的な関連性がないと判断される場合があります。
- 意味が人名として不適切:
- マイナスのイメージを持つ言葉:例えば「悪魔」「地獄」など、社会通念上、その子どもの将来にわたって不利益をもたらす可能性のある名前は認められません。過去には「悪魔」という名前が話題になりましたが、最終的には不受理とされました。
- 固有名詞:例えば、「トヨタ」「ソニー」といった、会社名や商品名など。
- 差別的な意味合いを持つ言葉:特定の民族や集団を侮辱するような言葉も認められません。
これらの判断は、最終的には市区町村の担当者や、場合によっては法務局の判断に委ねられます。そのため、一概に「この名前なら大丈夫」とは言い切れない部分もありますが、社会通念に照らして**「その子の人生に不利益をもたらす可能性が高い」**と判断される名前は、受理されない可能性が高いと言えるでしょう。
なぜ、役所は名前を制限するのか?
「親が自由に名前をつけられないなんておかしい!」と感じる方もいるかもしれません。しかし、これには重要な理由があります。
名前は、その個人を社会で識別するための、最も基本的な情報です。
- 社会的な混乱の防止:誰もが読めない、不適切な名前が横行すると、行政サービスや契約手続きなど、社会全体に混乱を招く可能性があります。
- 子どもの保護:あまりにも奇抜な名前や、意味の悪い名前をつけられた子どもが、将来いじめや差別、就職での不利など、不利益を被ることを防ぐための措置です。
つまり、役所が名前を制限するのは、親の権利を否定するためではなく、**子どもが社会で健やかに生きていくための「最低限のガードレール」**のような役割を果たしていると言えるでしょう。
正当な理由がないからと諦めないで、改名に最も有力なもの
通称として長年使用している
これが、改名が認められる理由の中で、最も有力なものです。
「通称の永年使用」とは、戸籍上の名前とは別に、社会生活で特定の名前を長期間(一般的には5年~10年以上が目安)使い続けている場合を指します。
例えば、戸籍上の名前は「太郎」なのに、幼い頃から周りの人にはずっと「ケン」と呼ばれていて、会社や友人関係でも「ケン」で通しているようなケースです。
なぜこれが有力な理由になるかというと、「すでに社会生活において、戸籍名ではなく通称名が本人を特定する名前として機能している」と認められるからです。
この場合、家庭裁判所に、通称名を長年使用してきたことを証明する資料を提出する必要があります。
- 公共料金の明細、年賀状、手紙、契約書
- 各種の招待状(結婚式など)
こうした資料を積み重ねることで、「この人は、もう通称名で生活している」という事実を説得力をもって示すことができます。
この方法であれば、「キラキラネーム」「しわしわネーム」関係なく改名をすることができます。
まとめ
かつてはキラキラネームの子たちが抱えていた悩みが、今ではしわしわネームの子たちにも広がっています。名前のことで「古臭い」「ダサい」とからかわれたり、一人でこっそり思い悩んだりしている生徒さんがたくさんいます。
でも、知っておいてほしいのは、名前は変えることができるということです。
改名手続きは少し大変かもしれませんが、自分の人生をより良くするために、前向きに考えられる選択肢の一つです。
一人で悩まずに、いつでも気軽に周りの大人に相談してみてください
保護者の方へ:名づけは、子どもへの最初の贈り物
お子さんの名づけは、お子さんへの最初の、そして一生の贈り物です。
キラキラネームにせよ、しわしわネームにせよ、そこには親御さんの深い愛情が込められていることを、私はよく知っています。
ですが、その愛情が、時に子どもにとって重荷になってしまうことがあるという現実も、お伝えしなければなりません。
そして、今の時代、キラキラネームの子たちは「いざとなれば改名できる」と知っているため、どこかに心の拠り所を持っています。一方で、しわしわネームの子たちは、「古風な名前は改名が難しい」と思い込み、一人で悩みを抱え込む傾向にあります。
名前は、お子さん自身が、自分の人生を歩んでいく上での土台となります。
お子さんが、その名前を誇らしく思えるように、そしてもし悩みを抱えたとき、いつでも親御さんに相談できるような、温かい関係を築いていただければ幸いです。




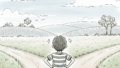

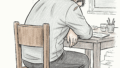
コメント